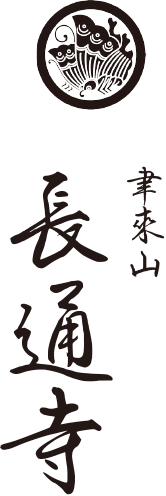読みもの
2025.10.03
戒名って
戒名については、現代でもいくつか意見があります。
最近では、生前の名前(俗名)のまま供養して欲しい、というお話をされることも多くあります。それぞれ思いなどありますが、皆さまも「戒名」とは?と改めて考えられる事もあるのではないでしょうか。今回はそのお話を少しさせていただきます。
仏教の始まったインド、そして中国には日本と同じような「戒名」という制度はなく、日本のような檀家制度もありません。しかし、インドでは、仏様の戒(教え)を受け仏道修行者となった者は「沙門○○」と呼ばれ、悟りを得た後の釈尊は大沙門と呼ばれ、ゴーダマ・シッダルダから「シャカムニブッダ・ゴーダマブッタ」となりました。中国においては、本人の「実名」を呼べるのは、父母国王のみで、お互いは「字名」を呼んでいたそうで、有名な人物では孔子を仲二と呼んでいたそうです。そのようなことから、出家者もそれにならい渾名が道号となり、本名では呼ぶことはなかったのです。
現代の日本でも目上の方を本名で呼ばないという文化はあり、例えば、どこどこの叔父さん、会社では社長、課長など役職名であり、呼ぶとしても名字で呼ぶ程度ではないでしょうか。
本人に置き換えても、年齢に合わせて呼び方は変わっていきます。○○ちゃんから、クンサンづけ、そして名字へと自然と変わっていきます。
このように名前は古来変化するものでありましたが、明治八年に「苗字必称令」で国家管理の都合上、四民等しく苗字を名乗らせると共に、名前を変えてはならなくなりました。
ですので、一つ立場が変わるごとに名前が変わるということはとても重要なことであり、その本人も周囲も「自覚」するという意味合いがありました。
また具体的に戒名とはなにか、それはお釈迦様のお弟子としてのお名前になります。釈尊第○○代目としても「戒名」をお寺の住職として、また僧侶として、一人のお釈迦様の弟子としてお授けさせていただきます。
これらのことから、仏様のお名前として「戒名」を授かるということは故人様もこの世に残る私たちもお釈迦様のお弟子となられたという「自覚」ともに持つためにも「戒名」は大切なのです。
この戒名につけられる文字がそれぞれあります。この選び方についても様々な意見がありますが、私が長通寺住職として大切にしていることがあります。それはこの世に残された皆様が戒名を見た際、生前姿を思い返していただけるような文字を選べられるよう考えています。そうした中で、お葬儀の打ち合わせの際には思い出話を聞かせていただき、そのお話を参考にお人柄、お仕事、ご趣味など様々な思い出からその方だけの「戒名」をお授けさせていただいています。
仏様のお弟子となられたお名前「戒名」ご先祖様の戒名改めてみていただき、ご先祖様への思い、今私たちが生きているという「自覚」を胸にお手を合わせていただけたら幸いです。
参考図書:「津送須知」滴禅会刊