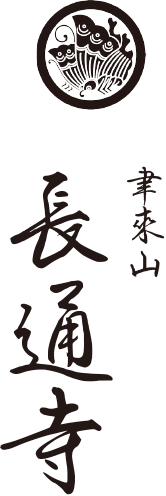読みもの
2025.11.01
お寺の豆知識「7日経って?」
お葬儀があるとよく耳にする「初七日」という法要。
最初の一週間だからお参りをするの?と思われる方もおられると思います。
しかし、本来この法要は「初七日」で終わるのではなく、四十九日まで七日七日お勤めをします。この法要を「七日経」と言います。
そして、この七日七日にはそれぞれ意味が込められています。
一・七日(初願忌(しょがんき))
故人様のこれからの七日七日のご供養・修行のご無事を初めて願う法要になります。
二・七日(以芳忌(いほうき))
仏様の一番のお食事はお香の煙になります。仏様、お釈迦さまに近づきお香をお食事とされる香食供養になります。
三・七日(酒水忌(しゃすいき))
無事に三途の川を渡ると言われています。文殊菩薩様に智慧の水を洒いでいただき、身も心も清めて仏様へと進んでいく供養になります。
四・七日(阿経忌(あぎょうき))
普賢菩薩様(心の安定、安らぎを司る菩薩様)に、阿弥陀様と同じように、光の存在となって見守ってほしいと願う行の供養です。
五・七日(小練忌(しょうれんき))
閻魔様による小吟味と言われています。そして、地蔵菩薩様の慈悲にて、苦しみを抜いていただく供養になります。
六・七日(檀弘忌(だんこうき))
弥勒様が来られるまで、残された私たちは追善の布施行(檀波羅蜜)を誓う供養になります。
※檀波羅蜜‥周りの人を大切に、思いやり真理を施す修行。
七・七日(大練忌(だいれんき))
一般的に言われている四十九日の法要。大いなる鍛錬を終えられ、自他ともに身心の安らぎを願う供養になります。主に納骨の時期とされ、お釈迦様、ご先祖様の仲間入りを果たされると言われています。
このように、内容には諸説ありますが、それぞれ意味が込められています。
近年ではご都合により省略される事が多くなりました。しかし、お参りができなくても、七日七日の節目、故人様がご修行されているということを知っていただくだけでも大きなご供養となるのではないでしょうか。
※参考文献「住職として学んでおきたいこと 著者 呉定明」