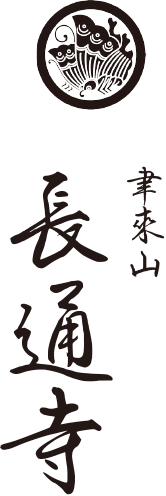読みもの
2025.11.01
お寺の豆知識「7日経って?」
お葬儀があるとよく耳にする「初七日」という法要。
最初の一週間だからお参りをするの?と思われる方もおられると思います。
しかし、本来この法要は「初七日」で終わるのではなく、四十九日まで七日七日お勤めをします。この法要を「七日経」と言います。
そして、この七日七日にはそれぞれ意味が込められています。
一・七日(初願忌(しょがんき))
故人様のこれからの七日七日のご供養・修行のご無事を初めて願う法要になります。
二・七日(以芳忌(いほうき))
仏様の一番のお食事はお香の煙になります。仏様、お釈迦さまに近づきお香をお食事とされる香食供養になります。
三・七日(酒水忌(しゃすいき))
無事に三途の川を渡ると言われています。文殊菩薩様に智慧の水を洒いでいただき、身も心も清めて仏様へと進んでいく供養になります。
四・七日(阿経忌(あぎょうき))
普賢菩薩様(心の安定、安らぎを司る菩薩様)に、阿弥陀様と同じように、光の存在となって見守ってほしいと願う行の供養です。
五・七日(小練忌(しょうれんき))
閻魔様による小吟味と言われています。そして、地蔵菩薩様の慈悲にて、苦しみを抜いていただく供養になります。
六・七日(檀弘忌(だんこうき))
弥勒様が来られるまで、残された私たちは追善の布施行(檀波羅蜜)を誓う供養になります。
※檀波羅蜜‥周りの人を大切に、思いやり真理を施す修行。
七・七日(大練忌(だいれんき))
一般的に言われている四十九日の法要。大いなる鍛錬を終えられ、自他ともに身心の安らぎを願う供養になります。主に納骨の時期とされ、お釈迦様、ご先祖様の仲間入りを果たされると言われています。
このように、内容には諸説ありますが、それぞれ意味が込められています。
近年ではご都合により省略される事が多くなりました。しかし、お参りができなくても、七日七日の節目、故人様がご修行されているということを知っていただくだけでも大きなご供養となるのではないでしょうか。
※参考文献「住職として学んでおきたいこと 著者 呉定明」
2025.10.03
戒名って
戒名については、現代でもいくつか意見があります。
最近では、生前の名前(俗名)のまま供養して欲しい、というお話をされることも多くあります。それぞれ思いなどありますが、皆さまも「戒名」とは?と改めて考えられる事もあるのではないでしょうか。今回はそのお話を少しさせていただきます。
仏教の始まったインド、そして中国には日本と同じような「戒名」という制度はなく、日本のような檀家制度もありません。しかし、インドでは、仏様の戒(教え)を受け仏道修行者となった者は「沙門○○」と呼ばれ、悟りを得た後の釈尊は大沙門と呼ばれ、ゴーダマ・シッダルダから「シャカムニブッダ・ゴーダマブッタ」となりました。中国においては、本人の「実名」を呼べるのは、父母国王のみで、お互いは「字名」を呼んでいたそうで、有名な人物では孔子を仲二と呼んでいたそうです。そのようなことから、出家者もそれにならい渾名が道号となり、本名では呼ぶことはなかったのです。
現代の日本でも目上の方を本名で呼ばないという文化はあり、例えば、どこどこの叔父さん、会社では社長、課長など役職名であり、呼ぶとしても名字で呼ぶ程度ではないでしょうか。
本人に置き換えても、年齢に合わせて呼び方は変わっていきます。○○ちゃんから、クンサンづけ、そして名字へと自然と変わっていきます。
このように名前は古来変化するものでありましたが、明治八年に「苗字必称令」で国家管理の都合上、四民等しく苗字を名乗らせると共に、名前を変えてはならなくなりました。
ですので、一つ立場が変わるごとに名前が変わるということはとても重要なことであり、その本人も周囲も「自覚」するという意味合いがありました。
また具体的に戒名とはなにか、それはお釈迦様のお弟子としてのお名前になります。釈尊第○○代目としても「戒名」をお寺の住職として、また僧侶として、一人のお釈迦様の弟子としてお授けさせていただきます。
これらのことから、仏様のお名前として「戒名」を授かるということは故人様もこの世に残る私たちもお釈迦様のお弟子となられたという「自覚」ともに持つためにも「戒名」は大切なのです。
この戒名につけられる文字がそれぞれあります。この選び方についても様々な意見がありますが、私が長通寺住職として大切にしていることがあります。それはこの世に残された皆様が戒名を見た際、生前姿を思い返していただけるような文字を選べられるよう考えています。そうした中で、お葬儀の打ち合わせの際には思い出話を聞かせていただき、そのお話を参考にお人柄、お仕事、ご趣味など様々な思い出からその方だけの「戒名」をお授けさせていただいています。
仏様のお弟子となられたお名前「戒名」ご先祖様の戒名改めてみていただき、ご先祖様への思い、今私たちが生きているという「自覚」を胸にお手を合わせていただけたら幸いです。
参考図書:「津送須知」滴禅会刊
2025.09.27
寺嫁日記〜令和7年夏号掲載〜
「親子の挑戦」
毎年6月7月と暑くなるたびにお寺はそわそわし始めます。住職も「今年の夏も暑いかなー、早くお盆の準備に取り掛からないとな」とぼそぼそとつぶやき始めます。私もこの時期になると夏をどうやって乗り越えようか、ということが頭の中をめぐります。
そんなお寺が一番忙しくなるお盆。今年は長男が「傘踊りがしたい」と、とんでもないことを言い始めました。去年の夏、子どもたちにも少しは地元の夏の風物詩を見せてあげたいなと思い、私も住職も最後の体力を振り絞って8月14日しゃんしゃん祭りへ連れて行きました。すると長男の通う小学校の連の息のあった見事な演舞を見ることができました。その様子を見ていた長男は「かっこいいな、やってみたな」と言うようになりました。お寺としては一年で一番忙しい時期。「こまった・・・」しかし長男は「絶対にやりたい!頑張るから!」と譲りません。住職も参加した経験はもちろんないので「大丈夫かな」と子どもの心配はもちろんお寺の心配もし悩んでいました。しかし、子どもの間しかできない経験かもしれません。「このチャンスを逃したら・・・何事もあきらめずに頑張って欲しい。よし。せっかくだからやってみよう」と親子で決断をし、挑戦してみることにしました。子どもの間しかできない経験かもしれませんし、鳥取の文化も体験してほしいという思いでした。
連に入り、練習が始まりました。長男も毎日熱心にタブレットを見ながら練習をしています。全体練習というものもありものすごい熱量。今までしゃんしゃん祭りに行ったこともなく、テレビでしか見る機会のなかった住職は「こんなに練習するんだな」と驚いている様子でした。曲数も一曲ではありません。足の角度、目線の向き、細かい動き一つ一つ覚えていきます。これをあの暑い中、3時間。長男は踊りきれるのだろうか、そして私はついて回れるだろうかという不安に駆られています。そして最大の問題。どうやって当日会場まで連れていくのか。集合時間はまだお寺で法要をお勤めしている時間。「これはまずい、そんなに早く集合するの?どうしよう・・・」そんな時「一緒に行こうよ」と友達の保護者の方に声をかけていただきました。本当にありがたいことです。しかも、真逆の方向から来てくださると。もしかしたら諦めないといけないかなとも考えていましたが、周りに助けられていると実感しました。
このお便りが皆様のもとへ届く頃は、本番へ向けた大詰めの練習の時期だと思います。私も住職もお寺のことでそわそわ、ばたばたしている、お盆のこの時期。お寺にお参りいただいたとき、もしかしたら長男が「しゃんしゃん」と練習をする鈴の音が聞こえているかもしれません。親子の挑戦。この夏も頑張っていきます。
2024.06.06
【全国曹洞宗青年会】災害復興支援活動 中国管区研修会
住職が出向させていただいています「全国曹洞宗青年会」の50周年記念事業としまして、災害復興支援活動 中国管区研修会が6月4日広島県福山市泉龍寺様にて開催されました。
災害時の炊き出し研修、また当日には「特定非営利活動法人災害救援レスキューアシスト」中島武志氏にお越しいただきまして、災害時のボランティアに入る上での心構えなど、現地で感じられて事をご講義いただきました。
私自身は東日本大震災を学生時代に東京で経験し、自信を含めた災害は人事とは思えませんでしたが、今回の能登の災害など実際にボランティアへ入ったことはありませんでした。
それには個人として、ハードルが高いように感じていたり、何か出来ることはないかと考えているだけで、前に進めていなことが多くあったと振り返っていました。
実際に現地へボランティアへ入ろうと思うと、やはりハードルは高いですが、離れていても出来る支援、義援金など、今できることを少しでも行なっていければと感じ、また学ぶことのできる機会となりました。
2024.03.17
佐世保施食法要【YouTube動画】
住職が出向しています、全国曹洞宗青年会。
この度、担当している教化委員会にて、長崎県佐世保市で行われている、お盆の施食法要を撮影させていただきました。
地域に風習によって違いのある施食法要。
佐世保市では太鼓にてお経のリズムをとる、全国でも珍しい法要となっています。ぜひご覧いただき、さまざま地域の法要に触れていただけたらと思います。